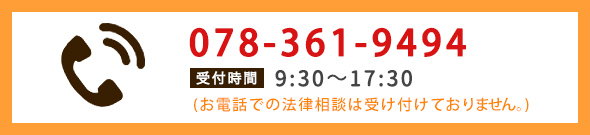Q:被相続人の長男の妻のように、相続権のない人が被相続人の療養看護に献身的に努めたような場合に、被相続人の相続にあたってその人の特別の寄与に報いる制度ができたと聞いたのですが?
A:
- 従来の寄与分制度の限界
従来より、被相続人が残した相続財産に関して、相続人の一部が労務の提供、財産の拠出、療養看護といった一定の事情により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたような場合には、寄与分と評価して具体的相続分の算定に反映させることが認められてきました。
(詳しくは解説編その5:寄与分)。
しかし、寄与分というのはあくまで相続人に認められる制度にすぎませんので、ご質問のような場合は、長男の妻の貢献を長男の寄与分として一定程度反映させて、長男の相続分を多くする、というのが、せいぜいのところでしたし、仮に長男が先に死亡していた場合は、長男の妻には相続権はありませんので、寄与分を認める余地はありません。 - 特別の寄与制度の創設
そこで、このたびの相続法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族については、特別寄与者として、相続人に対して一定の特別寄与料の支払を請求できる、という制度が創設されました(民法1050条;なお、2019年7月以降の相続に適用されます)。特別寄与が認められるための要件としては、まず第1に、被相続人の親族であることが必要です。第2に、寄与行為の態様としては、被相続人の療養看護をしたり事業を手伝ったりした場合などの、労務の提供をした場合に限られます。したがって、被相続人に何らかの財産上の給付・拠出をしただけという場合は除かれます。第3に、そうした労務の提供は、無償であったことが必要です。労務の提供に対して対価の支払いがあった場合は、それによって被相続人からの報いがその時点であったと評価されるからです。第4に、労務の提供によって「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」と言えることです。ですので、純粋な精神的援助にとどまるような場合は、認められません。
以上の要件からしますと、現実の態様としては、被相続人の親族の一人が被相続人の療養看護に相当期間にわたって無償で努め、それによって、もしも被相続人の介護・看護を第三者に依頼したとすればかかったはずの費用支出が抑えられ、その結果相当な財産が残った、というような場合が典型的でしょう。
- 特別の寄与があったと認められる場合の取り扱い
以上のような特別の寄与があったと認められる場合に、寄与をしたのが相続人であった場合は、従来どおり遺産分割にあたって寄与分を考慮して具体的相続分を算定するという扱いがなされますが、特別の寄与をした親族が相続人以外だった場合は、その親族が相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができるという扱いになります。その場合に、相続分が複数いるときは、各相続人は相続分に応じた負担をするということになります。 - 特別寄与料の具体的算定
特別寄与料の算定ですが、関係者間の協議によって決まらない場合は、家庭裁判所が、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他の事情を考慮して定めることになっています。目安として、療養看護による寄与の場合は、寄与分の算定の場合と同じように、第三者が同様の療養看護を行った場合の日当額に療養看護の日数をかけた金額をベースとし、これに相続財産の総額等を加味して決めるというようなことになるでしょう。 - 特別寄与料を請求できる期間
ただし、このような特別寄与料の支払請求は、被相続人が死亡して相続が開始したことや誰が相続人であるかを当該親族が知った時から6ヶ月以内、もしくは最長でも被相続人の死亡後1年以内にする必要があります。そのような短期間の制限がなされたのは、相続人間の遺産分割協議は相続人の相続分をベースにして短期間のうちになされることが多いので、それを実質的に修正するような特別寄与料の請求は、その前に行っておく必要があると考えられるためです。 - 専門家の必要性は?
親族による特別寄与料の請求については、寄与分が認められるかどうかの判断と同じように、高度な法的判断を求められる場合が多いと言えます。相当期間にわたる療養看護などの労務の提供をしたことによる財産の維持・増加ということについて、具体的に裏付ける根拠づけや、どの程度の金額が請求できるか、さらに誰にどのように請求をするか、といった判断も必要となります。相手が特別の寄与を否定した場合には、裁判所に調停や審判を申し立てることを念頭に置いた検討も必要になってきます。このような場合は、弁護士などの専門家に相談する必要性が大きいと言えるでしょう。